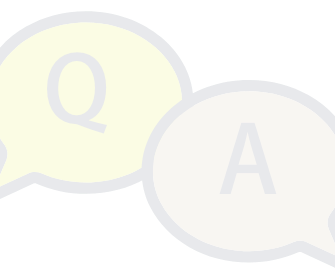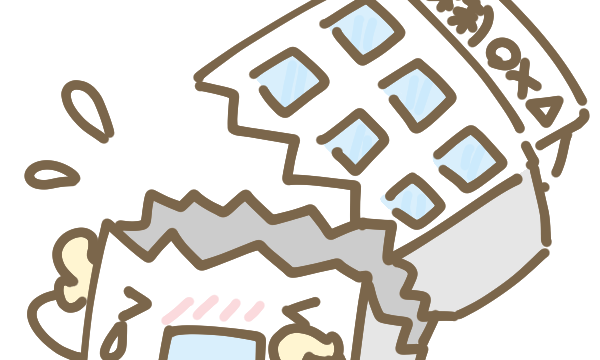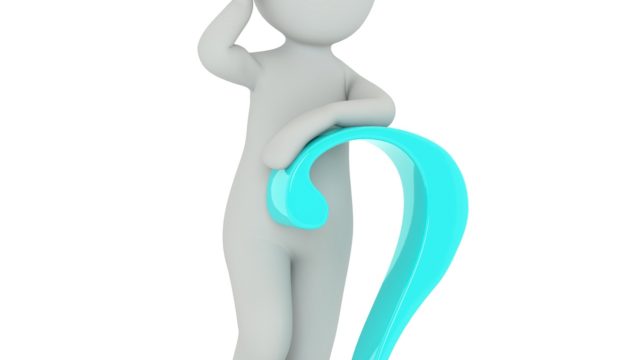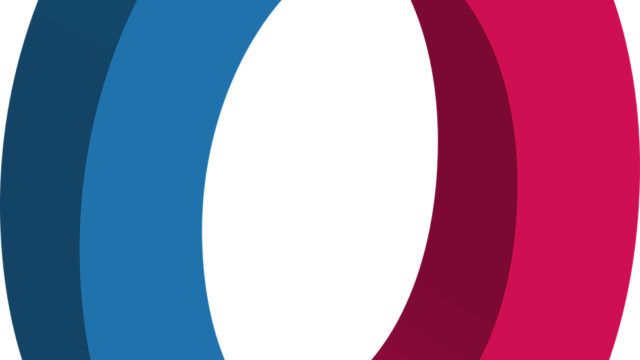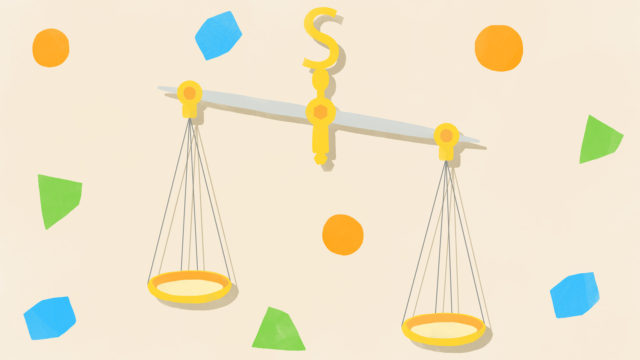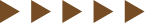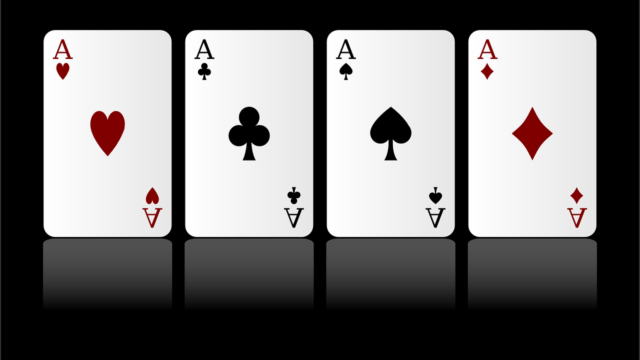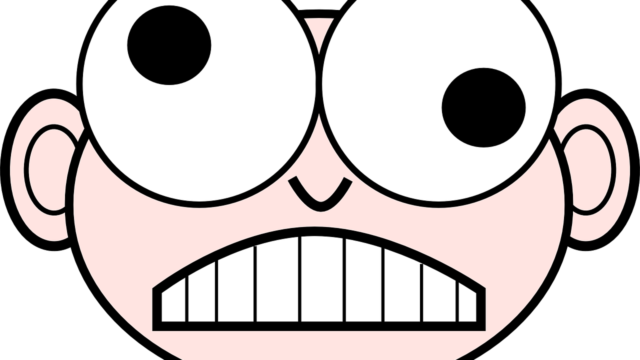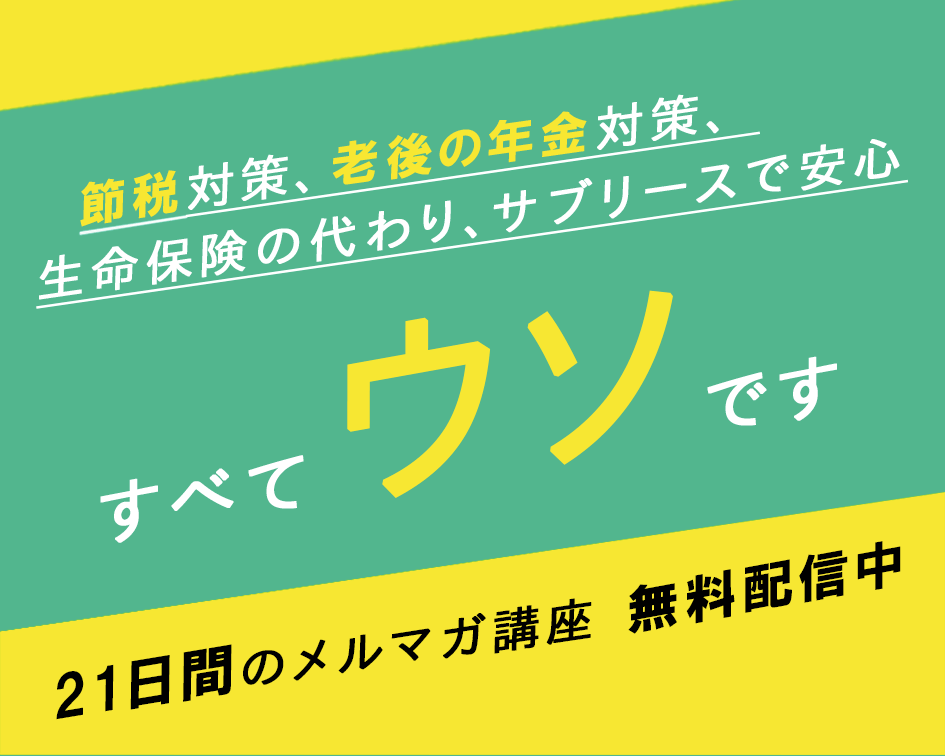大手証券会社の存在ニーズは、明らかに薄れている。
SBI証券、楽天証券などのネット証券があれば、個人投資家にとっては十分である。
大手証券会社が行っている、比較的資産のある高齢者層を、ある意味騙して手数料を稼ぐような商売は、続くはずがない。
若年層は、手数料やサービスの質の違いから、大手証券会社などを使うことは永遠にないだろう。
インターネットが使えるデジタルネイティブ世代は、豊富な情報量を持っているし、調べようと思えば、すぐにネットで検索できる。
大手証券会社は、若年層へアプローチすることはできず、今後も衰退していくであろう。
私は、そう遠くない未来で、Xデーは訪れると思っていたが、その未来は想像よりも早いかもしれない。
大手証券である野村證券、大和証券の最近の株価を見れば、よくわかる(2019年現在)。
日経平均は、比較的堅調に推移しているのに対し、証券会社の株価はどうだろうか。
野村證券の株価は、350円前後(2019年5月)
大和証券の株価は、480円前後(2019年5月)
今までの株価推移でみると、リーマンショック時の水準に近いくらいまで落ち込んでいる。
日経平均は、リーマンショック時から、倍以上になっているにも関わらずだ。
本来証券会社の株価は、日経平均に連動してしかるべきだった。
景気が良いので証券会社の利益も大きくなる、という流れだ。
しかし、今は明らかに違う。
株価は素直だし、先を示す指標になるなと改めて感じる。
積極的な買い材料が極めて乏しい業界の株を買わないのは、ある意味当然かもしれない。
大手証券会社の社員は、来るXデーを迎えた時、個人の能力が問われるであろう。
独立して食える力があるのか
高い給与が得られる会社に転職できる力があるのか
日ごろからの努力と自分の実力が試される時がくるだろ。
中年以上のお荷物社員は要注意だ。
今から自分には何ができるのか、日々努力して、いつなにがあっても問題ないように備えておくべきだろう。
週刊現代
2019年5月22日掲載
1004億円の最終赤字――。2018年度決算で野村ホールディングスは巨額の損失計上を余儀なくされた。もちろん、トップ証券の座からの転落である。背景にあるのは国内外における事業の不振である。
そこで、いま、同社は事業モデルの再構築に動き出した。海外では各拠点の縮小などを加速させ、国内では店舗の統廃合を急ぐ。一方、国内では不祥事が相次で発生した。いったい、資本市場の圧倒的な存在として君臨し続けてきた野村に何が起きているのか。野村ホールディングスの永井浩二・グループCEOを直撃インタビューした。
(取材・文:浪川攻/写真:西崎進也)
〔photo〕インタビューに答える永井CEO
ビジネスモデルが崩壊した
――前年度は巨額の赤字だった。なぜか。伝統的な投資銀行モデルが世界中で崩壊してしまった。商業銀行とのミックス形態のビジネスモデルはなんとか健闘しているが、海外では典型的な投資銀行ビジネスを営む一方で、国内では伝統的なブローカレッジハウスであるという組み合わせである当社はこの一年、残念ながら、まったくいいところはなかった。
――確かに、伝統的な投資銀行モデルは世界的にみて絶滅危惧種とすら言われている。
リーマンショック後の景気落ち込みに対処するために、世界的に中央銀行による金融緩和が行われてきた。財政政策に限界性があるため、先進国は金融政策に依存する経済政策を強化した。それによって、いずれ、経済が回復すれば、金融政策も正常化するだろうと考えられてきたが、予想外に状況は戻らなかった。
2014年からFRB(米連邦準備理事会)が量的緩和の出口政策であるテーパリングを開始したので、私もこれでようやく正常化に向かうと思っていたのだが、その後、次第にそれとは異なる情勢に変わっていった。それが最も明確化したのが昨年末のFRBによる政策姿勢の転換だった。量的緩和をやめ、徐々に市場と対話しながら正常化に向けて金利を引き上げていたが、その政策スタンスを放棄してしまったと言える。これによって、当面、正常化は遠のいたことが決定的になった。
先進国の中央銀行が市場から債券を吸い上げ、しかも、金利はほとんどゼロか、マイナス水準である。機関投資家には債券売買する意味がなくなっている。自社のバランスシートにレバレッジをかけて、お客様が買いたい銘柄を自らの在庫から提供し、売りたいお客様からは引き取ると言う流動性の供給業者(リクイディティ・プロバイダー)の意味もなくなってしまった。当社はその一社にならない。
元には戻れない
――しかし、そのリスクは昨年末よりも相当に早い時期から潜在していたはずだが。その通りだ。皮肉にも、その結果として、当社のバランスシートの健全性は格段に向上して、自己資本はTier1レベルで18%という、いわば、製造業並みの高いレベルとなった。しかし、このような環境がずっと続いたら、経営は行き詰まりかねない。したがって、根底からビジネスモデルを変えざるを得なくなった。
じつは、かなり以前から欧州は厳しいと考えていた。とくに、2年前にブレクジットが起きて、その思いはなおさら強まっていた。当社は経営資源をロンドンに集中させていただけに、その態勢の抜本的な見直しが不可欠になった。だが、当社が取り組んだリストラはビジネスの集中と選択だった。これは、いずれ、状況がもとに戻れば、元の態勢に復元するということを前提にしていたものだった。しかし、もはや、元には戻れないと確信した。戻れないし、戻らない。リクイディティ・プロバイダーとしての役割の出番は当面やってこないだろうと。
――結局、野村は絶えず変化する市場と社会の動きにキャッチアップできていなかったではないか。
そう言わざるを得ない。キャッチアップできていたら、こんな事態にはならなかった。
――新戦略を巡っては、リストラによるコスト削減が話題になっているが、むしろ、聞きたいのは、野村グループはどう変わるのかということだ。この点はどうなのか。
メガトレンドが変わらないという前提に立つ限り、ホールセールのなかで大きなシェアを占めてきたセカンダリートレーディングに成長は期待できない。シェア拡大は目指さず、資本投下も控える。代わって、プライマリー、アドバイザリー系にリソースはシフトする。ここは十分にディールができている分野だ。
――プライマリーとセカンダリーは密接なはずだ。実際、野村は強大なセカンダリーマーケットパワーでプライマリーを支えてきた。
その通りだ。セカンダリーは米国ですら3%強のシェアを有している。しかし、米国の投資銀行ではこの数年、グローバルマーケッツのビジネスをまったくやらずに、アドバイザリーだけを提供しているハウスもかなり出ている。ラザード社などがそうだ。
確かに、プライマリーの展開にはセカンダリーの基盤がある程度構築していることが条件と言えるが、セカンダリーは機関投資家のビジネスだけではない。当社はリテールを含めて強みがある。これを放棄するつもりはまったくない。
もう我慢の限界
――しかし、その国内リテール部門に強さの陰りがないか。むしろ、それは意思をもってやってきた結果だ。「熱血営業」等々、かつてのやり方は志向しない方針を貫いているのだから。
リテール分野における顧客基盤のひとつは、年齢が比較的高い富裕層――金融資産で数億円以上――であり、この階層は当社にとってはきわめて大切なお客様だ。この階層が抱いている最大のニーズはトータルの資産をいかにうまく次世代に承継するかである。それに応えるべく、当社はこの数年でプラットフォームを構築し強化してきた。結果として、国内では最も強いハウスとなったと自負しているし、この階層からはきわめて評価を得ている。
しかし、もうひとつのマスアルフエント(準富裕層)は、まったく力を入れてこなかった。当社は530万口座を有する日本最大のオンライン業者である。オンライン口座の契約数も、口座に残高があるベースで350万口座を数える。預かり資産も約35兆円ある。日本最大級のオンラインプラットフォームなのだが、従来、まったく、ここに力を入れてこなかった。
〔photo〕gettyimages
――なぜなのか。当社のリテール部門が興味を持たなかったからだ。この分野で稼げるとは思っていないからだ。富裕層には痒いところに手が届くようなサービスを提供している一方で、非対面のマス層にはあまりにも興味を抱かずにきた。したがって、サービス内容には競争力が伴っていない。私は2、3年前から「積み立て型の長期累積投資への取り組みが将来、盛衰を決するぞ」と担当役員にも言ってきた。しかし、率直に言って、彼らの動きは鈍かった。
――不思議なことだ。なぜ、トップが言っても現場は動かないのか。
センスがないからだ。そこで、今回、見切りをつけた。伝統的な国内ブローカレッジが強いという社内カルチャーに埋没しているなかでは、新たなことに取り組む人は育たない。カルチャー、伝統が邪魔してしまうからだ。
私は2年間我慢した。しかし、もはや、限界を超えた。社内の人材ではダメならば、外部の人材を活用する。ちょうど、2015年12月に私の直轄で金融イノベーション推進支援室(FIO)を社内外の公募で立ち上げている。これと同じ形でやることにした。
たとえば、2018年春に実現したLINEとの提携も社内では議論があった。この提携では当社が49%出資のマイノリティという立場である。かつての当社であれば絶対に組まなかった条件だ。現に、社内には「51%超でないと組む意味がない」という意見も相当あったが、私は説得し押し切った。もちろん、できるならばマジョリティ出資のほうが理想的だが、いまはそんなことを言っている場合ではない。
我々は潰れる恐怖と戦っている
――勝ち目はあるのか。当社の顧客口座数は証券業界でナンバーワンであっても、大手銀行の預金口座数の8分の1足らずしかない。それではお客様の裾野は広がらないのだから、自前でいくらやっても勝ち目はない。しかも、地道な努力ができるのか。たとえば、駅頭で口座新設に向けたチラシ配りに汗を流せるのかといえば、配れないし、配る気もないだろう。LINEは約7900万人のユーザーがいる。ところが、彼らには提供する金融サービス、プロダクトがない。我々にはそれがある。
――ビジネス改革よりも社内改革のほうが先決な感じがするが。社員には何を腹落ちさせようとしているのか。
端的に言うと、赤字の会社である事実を認識せよと訴えている。部店長会議でも、潰れるとまでは言わないまでも大変な状態であると語った。社内に危機感がまったく足りないからだ。しかし、我々は潰れる恐怖と戦っている。
もちろん、現場の社員のモチベーションという問題にも関わるので、「ウチの会社は本当に大丈夫か」というムードがあまりにも強まれば、それは問題である。しかし、純粋民間会社である以上、「親方日の丸」的に潰れるわけがないと思われても困る。いまはどちらの雰囲気が勝っているかといえば、明らかに後者のほうだ。
ご存知のように、当社は給料水準が高い。福利厚生も充実している。なぜかといえば、他人よりも働いたからだ。みんなが必死になって働いたからだ。裏返して言えば、赤字が続けば、良好な給料水準をエンジョイできなくなる。それが資本市場の論理でもある。当社はその論理で動いている以上、そうなるしかない。であれば、生産性を上げるしかない。
――1年を振り返ると不祥事が目に付いた。これも社内のムードと関連するのか。
その問題は取締役会などでも幾度となく議論した。「なぜなのか」「なぜ、こんなことが起きるのか」と。いろいろと要因は出てくるのだが、何かひとつ、これが原因であるとは言えない。会社全体の状況が複合的に重なって起きている。もちろん、現場の規律の緩み、風紀の乱れ、プロとしての認識の甘さ等々、経営としてはもろもろのことに看過できない。
それにしても、お客様のおカネの着服事件など信じられないような内容ばかりだ。もちろん、経営の責任は免れないが、本当に唖然とさせられた。
絶対に起きてはいけないこと
――このような事件の発生は信用商売として致命的だ。その通りだ。「一時的な赤字で会社がすぐに潰れることはないが、社会の信用を失ったら、あっという間に潰れるぞ」と部店長会議でも強く訴えた。じつは、2年前の部店長会議でも冒頭に同様のことを話した。年に1、2回の部店長会議は全店サテライトでみている。その場で経営者がそんな話をせざるを得ないことは、まさに恥を忍んでということだ。本来あれば、「日々の業務、ご苦労様」と労うところだが、それを言わずに、「このままでは潰れるぞ」と語らざるを得なかった。きわめて恥ずかしいことだ。
――東京証券取引所の市場構成の見直しでも情報漏えい事件を起こしている。
それも含めて、部店長会議で訴えた。着服の事件があったうえに、あのような事態を起こしてしまった。資本市場の公正性の生命線である仕事に携わっている野村の社員としての意識の欠如が露呈したと言わざるを得ない。当社は2012年の増資インサイダー事件を引き起こして、社内で厳しい議論が行われたのにもかかわらず、だ。
あのときのことを忘れたのかと。不祥事は一人が引き起こしても、一人だからいいだろうという話ではない。なかでも、このような問題は絶対に起きてはいけないことだった。何万人、何十万人の社員、関与者がいても、絶対に起きてはいけない。我々はきわめて重大なことだと認識している。